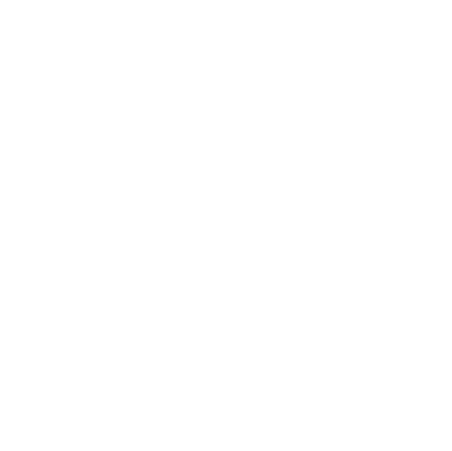旅するバレエ
イサドラ・ダンカン、その踊りは人生そのもの。パリに残る彼女の「かたち」
~フランス・パリ~
2025年2月、NHKバレエの饗宴2025でフレデリック・アシュトン「Five Brahms Waltzes in the Manner of Isadora Duncan」が上演された。英国を代表する振付家が20世紀初頭に一世を風靡した女性ダンサー、イサドラ・ダンカンをテーマにして創作したものだ。彼女の踊りに魅了され、創作意欲をかき立てられた芸術家は彫刻家のロダンをはじめ、絵画、文筆等々多様な分野にわたる。アメリカからフランスに渡り、欧州で一世を風靡しフランスで生涯を終えたイサドラは、現在パリに眠っている。

イサドラ・ダンカンをモデルにしたといわれるシャンゼリゼ劇場のレリーフ(アントワーヌ・ブールデル作、1913)
1900年のパリにセンセーションを巻き起こす裸足のダンサー
筆者が2018年にパリのロダン美術館を訪れたとき、「Rodin et la danse(ロダンとダンス)」という特別展を開催していた。そこに展示されていたのはダンサーの彫刻や習作のブロンズ、粘土細工、数々のスケッチで、モデルとなった人物には「ロイ・フラー」「ニジンスキー」、そして「イサドラ・ダンカン」らの名が並んでいた(※これらの作品は非常設)。
彫刻家――いわばモデルを介して静止の瞬間を造形する者が、躍動し続けるダンスという芸術を「かたち」としてとどめたいと思索することは、自身の芸術に対する大いなる挑戦だったのではないかと想像する。それほどまでに彼女らの踊りは芸術家の創作意欲を刺激してやまなかったのだろう。
今回のテーマであるイサドラ・ダンカン(1877-1927)は「モダンダンスの祖」として、また、その自由奔放な生き方で今なお伝説的な存在として語られる人物だ。1900年にパリに渡ったイサドラがチュチュではなく、ギリシャ風の緩いチュニックを身にまとって「心も身体も自由に解き放ち」肢体をさらけ出して裸足で踊る姿は、20世紀の声を聴いたばかりのヨーロッパ社会では裸で踊るに等しいほどに、相当にセンセーショナルであったに違いない。大勢の観衆を集めたというが、芸術としての視点ではなく、興味本位や眉唾モノ的な目も無論あっただろう。だが、わかる人にはわかる、刺さる人には刺さるというのだろうか。アシュトンは回想録で「(彼女の踊りを)好きになるとは思わなかったが、すっかり魅了されてしまった」と記し、ロダンは「彼女の芸術が私の仕事に与えた影響は他のどんなインスピレーションより大きい」と語ったという。
 |
 |
パリ7区、廃兵院を望むロダン美術館 ⒸTomoko Nishio ギリシャ風の衣装をまとったイサドラ
イサドラの生涯は、世界を舞台としたアメリカンドリームの具現者ともいえるかもしれない。
東から西へ、いよいよフロンティアも消滅しようというアメリカ西海岸のサンフランシスコで、1877年、銀行家の父、芸術家の母のもと、4人きょうだいの末娘としてイサドラは生まれる。が、父の銀行が破綻し浮気も発覚したのを機に、母は離婚し子どもたちを連れてオークランドへ。13歳のイサドラは生計を助けるために近所の子どもたちにダンスを教えていた。18歳で劇団員になるが、現状に満足せず欧州へ渡ることを決意。まずはロンドンに向かい古代ギリシャの芸術にインスピレーションを得て1900年、パリへ上陸した。
パリで当時話題となっていたダンサー、ロイ・フラーや彫刻家のロダン、ロダンの弟子ブールベルなど、多様な芸術家と交流を持ち先述のようなダンスで一躍話題の人物となる。ハンガリー、ウィーン、念願のギリシャへと旅をし、サンクトペテルブルクではのちにバレエ・リュスを旗揚げするディアギレフに会い、ニジンスキーらも彼女の踊りに大いに触発されたという。ダンサーとして活躍する一方で、ベルリンやパリ、モスクワにバレエ学校を設立し、自身のダンス哲学も広めていった。
踊りと同様私生活も自由奔放ではあるが、幸福と不幸のせめぎ合いでもあった。著名人との恋愛話は事欠かず、2人の婚外子を設けるが1913年、子どもたちを乗せた車がセーヌ川に転落し2人を同時に失うという不幸に見舞われた。この悲劇を機に、イサドラは世界中の子どものための教育により、心を傾けるようになったという。22年に出会ったロシア(当時はソヴィエト連邦)の18歳年下の詩人、セルゲイ・エセーニンとの恋も有名であるが、23年には破綻。そして27年9月14日、フランスのニースで事故によりこの世を去る。彼女が首に巻いていたスカーフがオープンカーのホイールに巻き込まれ、路上に投げ出されるという、悲劇的な顛末であった。
 |
 |
イサドラと子どもたち イサドラの最後の住まいはニースのネグレスコ・ホテルだった
60年代に再び世に。後世の芸術家にも影響を与え続ける
彼女の名が再び世に出はじめたのは1960年代のことで、ドキュメンタリーや映画「裸足のイサドラ」(1968)がきっかけの一つとだとされる。バレエ作品としてはモーリス・ベジャールがマイヤ・プリセツカヤのためにバレエ「イサドラ」を創作したほか、先述のアシュトンが1975年「Five Brahms Waltzes in the Manner of Isadora Duncan(イサドラ・ダンカン風のブラームスの5つのワルツ)」を、ハンブルク州立歌劇場のニジンスキー・ガラで発表した。これは同劇場の元芸術監督、ジョン・ノイマイヤーとリン・シーモアの依頼によるもので、当初はブラームスのワルツ第15番に振付したものだったが、翌76年、曲数を増やし、ロンドンのサドラーズ・ウェルズ劇場のバレエ・ランベール50周年記念ガラで初演された。
アシュトンがイサドラの踊りを目にしたのは1921年で彼が17歳の時。創作までに50年以上が経っている。アシュトンが実際に目にしたというバラの花びらを撒くパート以外は彼の記憶から膨らませたイサドラをベースにしており、それゆえに「ダンカン風の」とされているのだろう。奔放な印象を持たれるイサドラだが、アシュトンは「彼女は一般的に想像される俗っぽさというよりは、とても真面目で、非常に強い個性を持っていた」とも振り返っている。「ダンカン風」である以上、この作品から何を感じるかは踊る者・見る者次第だが、個人的にはイサドラの悲喜こもごもの人生や母としての思い、踊ることへの情熱が静かに凝縮されているのではないかと思う。人生経験を積んだ実力のある、熟練のダンサーが踊るほどに、味わいが増しそうだ。
さて、最後にまたイサドラ自身について話を戻せば、ニースで非業の死を遂げた彼女の遺骨は今、パリのペール・ラシェーズ墓地の納骨堂に収められており、すぐ近くのブロックには彼女が愛した2人の子ども、ディアドルとパトリックも眠っている。イサドラの踊りは彼女の心から湧き出る人生そのものであったろう。アシュトンの「ダンカン風」の通り、我々は彼女の伝記や自伝、同時代の芸術家や後世の作品を通して、時代を席巻した一世一代のダンサーに思いをはせるのみである。
その同時代の芸術家の作品のひとつが、1913年に完成したパリのシャンゼリゼ劇場の外観を飾っている。このレリーフは彫刻家ブールデルの作品で、ミューズの姿はイサドラがモデルとされている。パリのモンパルナスタワーの近くにあるブールデル美術館では、彼が描いたイサドラのスケッチが展示されている。踊りの映像がほとんど残らない彼女の「動き」を想像できる、数少ない場所の一つだ。
 |
 |
ブールデルによるイサドラ・ダンカンのデッサン ペール・ラシェーズ墓地にあるイサドラの墓
参考文献:
「オックスフォード バレエ・ダンス事典」/デブラ・クレイン、ジュディス・マックレル・著/鈴木晶・日本語版監訳/平凡社(2010)
「魂の燃ゆるままに――イサドラ・ダンカン自伝」/イサドラ・ダンカン・著/山川亜希子、山川 紘矢・訳/富山房インターナショナル(2004)
「美の女神イサドラ・ダンカン」/クルツィア・フェラーリ・著/小瀬村幸子・訳/音楽之友社(1988)
「パリの女たち 旅をする女」/海野弘・著/河出書房新社(1994)
「私を探す旅 イサドラ・ダンカンを追って」/松原惇子・著/文藝春秋(1995)
Five Brahms Waltzes in the Manner of Isadora Duncan
https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Brahms_Waltzes_in_the_Manner_of_Isadora_Duncan
Isadora Duncan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isadora_Duncan
https://www.navigart.fr/bourdelle/artwork/emile-antoine-bourdelle-isadora-dansant-190000000011164
Art & Travelライター
西井上知子