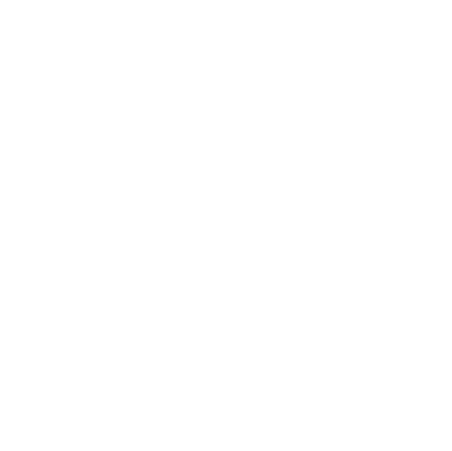旅するバレエ
「くるみ割り人形」 ~ドイツ~
おそらく世界で最も愛されているバレエ「くるみ割り人形」。軍服を着込んだ円筒形の体躯に逆三角のギョロっとした目、立派な前歯を持ついかつい顔のくるみ割り人形は、ドイツ南東部の「おもちゃの村」ザイフェンで生まれました。
今回はこの人形の誕生にまつわるエピソードをご紹介します。
舞台鑑賞のちょっとしたエッセンスにいかがでしょう。
錫鉱石から木のおもちゃづくりへ
ザイフェンが位置するザクセン州エルツ地方は1000メートルを超える山々とエルベ川が隣国チェコと自然の国境をなす山岳地帯で、州都ドレスデンからは車で1時間半ほど。人口2000人ほどの村人は今でも何かしらのおもちゃ産業に従事しているとか。さらに現在では山岳リゾート地・保養地として世界中の観光客が訪れています。くるみ割り人形がつくられはじめたのは18世紀頃ですがこの当時、この地方は冬場になると深い雪で覆われる、山間の貧しい地域の一つでした。
そもそもエルツ山地は鉱山地域で、12世紀に銀鉱が発見されたのを機に、錫、鉛、石炭などを産出し、ドレスデンを中心とする都市文化の発展を支えてきました。ザイフェンでは主に錫鉱石の採掘が行われていましたが、18世紀初頭に衰退。戦争や、時の為政者らによる重税などで生活が圧迫され、大人は煙突掃除夫や出稼ぎとして、子どもたちですら教会前で歌うことで日銭を稼ぐといったこともありました。そうしたなか、経済打開策として村人たちが取り組んだのが木のおもちゃづくりだったのです。
もともとザイフェンでは鉱山に入れない冬季の収入源として、ろくろ式の木工旋盤技術――日本のこけしの制作と似た技術――を利用したおもちゃや家具づくりの内職が行われていました。旋盤技術によりまとまった数の品がつくれるうえ、近郊にはドレスデン、さらに今なら車で3時間ほどの距離にニュルンベルクといった大流通市場があり、安価で質の高いザイフェンの木のおもちゃは、そこで民芸品、工芸品として取引されたのです。
 ザイフェンでつくられる木のおもちゃ ©︎Tourismusverband Erzgebirge e.V. ザイフェンでつくられる木のおもちゃ ©︎Tourismusverband Erzgebirge e.V. |
 ザイフェンのおもちゃ工房 ザイフェンのおもちゃ工房 |
木の人形とドレスデンのバロック文化は表裏一体
ザイフェンのおもちゃのモチーフは煙突掃除夫を模った煙を吐く人形、子どもの合唱隊や天使、クリスマス用のアーチ型キャンドル、あるいはろくろを巧みに使った木々のオーナメントや森の動物たちなど、職人たちの生活に根差したものが主でした。手で握るハンドル式のくるみ割り器も生活必需品として制作されているなか、1730年頃に実用を兼ねたおもちゃとして、人の形をした「くるみ割り人形」が誕生したといわれています。
かわいらしい子どもの合唱隊人形にくらべ、くるみ割り人形は着ているものこそ役人や兵隊、王侯貴族を思わせる立派なものですが、風貌はいかつく醜いものでした。これは一説によると、職人たちのうっぷん晴らしの意味合いもあるのだとか。重税にあえぐ村人たちが「役人どもに固い胡桃でも食わせてやれ」という思いを込めたといわれています。ちなみに彼らに重税を課した王の一人が、ザクセン選帝侯アウグスト2世(1670-1733)。華麗なバロック都市ドレスデンの礎をつくり芸術文化を発展させマイセン磁器も庇護した、ドレスデン全盛期の王です。世界に誇る宮廷文化と芸術が生み出された一方で、庶民が重税に苦しんでいたわけですが、王侯貴族のバロック文化と庶民の木のおもちゃはコインの裏表のような存在であることも頭に留め置きたいものです。
 ザイフェンでつくられるアーチ型のキャンドルたて。歌う子どもたちがあしらわれている。 ザイフェンでつくられるアーチ型のキャンドルたて。歌う子どもたちがあしらわれている。写真提供:ドイツ観光局 |
 いかつい顔をしたくるみ割り人形 ©︎Tourismusverband Erzgebirge e.V. |
クリスマスの童話から、世界的バレエの立役者に
さて、このうっぷん晴らしの人形は19世紀初頭に、E・T・Aホフマンの童話「くるみ割り人形とねずみの王様」(1816年)の登場で「クリスマスの立役者」という新たな個性が付け加えられます。
ドイツ文化圏はクリスマスマーケットの伝統があり、国内最古のクリスマスマーケットはそれこそ1434年にドレスデンで開かれたものといわれています(ちなみにドイツのクリスマス菓子シュトーレンもドレスデン発祥)。ドイツのクリスマスは日本の正月同様遠方に散っていた家族が帰省し、クリスマスツリーを飾ってプレゼントを贈り合います。こうした伝統のなかでE・T・Aホフマンの童話は市民社会に浸透し、くるみ割り人形は子どもたちに夢を与える存在として、ドイツ家庭の一家団らんの一員となりました。さらに1870年頃、ザイフェンの木工師ヴィルヘルム・F・フュヒトナー(1844 – 1923)が制作したくるみ割り人形は装飾性やデザイン、一説には人気絵本の挿絵からインスパイアされたという親しみやすさも手伝って人気となり、現在もっともよく知られる人形の原型となります。そして1892年、ロシアでプティパ台本、イワノフ振付、チャイコフスキー作曲のバレエ作品「くるみ割り人形」が誕生。サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で上演されたこのバレエとともに、くるみ割り人形も世界へと広まっていったのです。
 マリインスキー劇場での初演版第1幕(Wikipedia) マリインスキー劇場での初演版第1幕(Wikipedia) |
 Nutcracker1892.jpg) 同初演版第2幕。金平糖の精と王子(Wikipedia) 同初演版第2幕。金平糖の精と王子(Wikipedia) |
ザイフェンには現在も100を超える工房が昔ながらの手法でおもちゃをつくっており、「エルツ山地のくるみ割り人形の父」と称されるフュヒトナーの工房も8代目がザイフェン郊外で制作をつづけています。
ザイフェンのおもちゃ博物館では伝統的なおもちゃをはじめ、おもちゃづくりの歴史やデザイン画などが展示されているほか、ワークショップが開かれていることも。さらにザイフェンから5キロほど離れたノイハウゼンの村には個人が蒐集した「くるみ割り人形博物館」があり、ギネスブックに登録された、高さ10.10メートルの世界最大のくるみ割り人形が出迎えてくれます。機会があればぜひ現地で、山々の澄んだ空気や木々のぬくもりとともに本場の「くるみ割り人形」の世界にふれてみてください。クリスマスマーケットが開かれる頃に訪れ、ドレスデンの歌劇場ゼンパーオーパーでバレエ「くるみ割り人形」も鑑賞してみたいものです。
 クリスマスのイルミネーションが彩るバロック都市ドレスデン 写真提供:ドイツ観光局 ©Jörg Schöner
クリスマスのイルミネーションが彩るバロック都市ドレスデン 写真提供:ドイツ観光局 ©Jörg Schöner
Art & Travel ライター
西尾知子